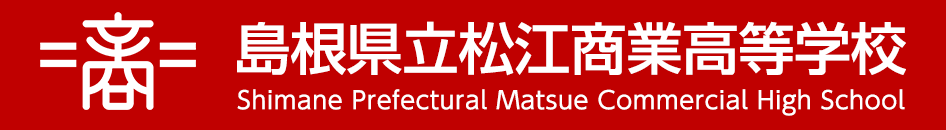令和6年3月22日(金)、体育館で終業式を行うことが出来ました。長いコロナ禍や天候の影響などで、リモートによる始業式や終業式が続いていましたが、いよいよこれからはこれが当たり前の式になるのでしょう。また、世の中も本格的に動き出してきました。今回は、その終業式での挨拶を元に述べてみます。
ここ数年間はあらゆる学校の教育活動が新型コロナウィルスの影響を受けてきました。校長の話はなかなか覚えてもらえないのが相場なので、折に触れ何度も繰り返して言い続けたことは「伝統の継承」と「未来の創造」でした。先ずは、コロナ禍で途絶えたものを「いかにして、何をどこまで復活させるか」という課題でした。教職員一同、生徒一同、前例を発掘しながら、次々と様々なものを復活させ実施してきました。これらについてはその都度紹介してきましたので今回は略します。そして、現在は「新しい魅力として何をどのように作って行くか」という課題が進行中です。しかし、その前に一つ確認しておきたいことがあります。『老子』に次のような言葉があります。
「 千里の行も足下(そっか)より始まる 」
(どんな遠大な計画でも、まず手近なところから始まる。)
新しい物事にチャレンジしてほしいですが、その前に自分の足元を見てください。自分が将来に向かって伸びていく基礎はできているか。学習や資格取得に対する取り組みはどうだったか。部活動や課題に対して地道に努力してきたか。そこを疎かにして成功はあり得ませんね。春休みは自分の足元を固めて将来への準備を始めましょう。
そして、チャレンジを始めたとしましょう。でも、うまくいかないことは世の常です。そんなときはこんなふうに考えてみませんか。
「 果報は寝て待て 」「 待てば海路の日和あり 」「 人事を尽くして天命を待つ 」
いずれも頷けるものの、微妙にニュアンスが違いますね。私は、「十分努力した上で結果を待つ」しかも「結果」といっても「良い結果」ならば喜び、たとえ「悪い結果」であっても反省材料として次に活かす、という点で3つ目のことわざを支持します。チャレンジ精神、忍耐力、前向きな姿勢が必要といったところでしょうか。
さて、今年は5月にコロナが5類に移行したおかげで、出張も多くなり、多くの人との付き合いが増えてきました。夏には振商会の東京支部と大阪支部に出かけて卒業生の方々とお話をしました。中には、「春には松商に求人に行くから待っていてください」と言われる社長さんもおられました。また、市内で、「今年は大卒ばかりでなく、高卒を採用したい」と言われる方もおられました。共通するのは、松商の生徒のイメージが、挨拶がきちんとできて簿記などの資格を持っており即戦力になる、というイメージだということです。これは先輩達が作り上げてくれた財産であり、襟を正し受け継がなければならないことだと思います。
3年生が卒業して、これからは1、2年生の皆さんが学校生活を支えていきます。来週には新入生オリエンテーションが開かれ、たくさんの生徒がやって来ます。しっかりと導いてあげてください。新入生に対して恥ずかしくない先輩としてどうあれば良いですか。これからは今までよりも地域や学校外の人との関係も多くなってくるでしょう。それだけ新しい出会いもあり、チャンスも広がってくるでしょう。あなたはどんな未来を想像しますか。春休みの宿題として自ら考え、決意も新たに新学期がスタートでき、令和6年度がさらなる飛躍の年になることを願っています。
最後に、私ごとで恐縮ですが、今年度をもって松江商業高等学校の校長を、同時に島根県商業教育研究会の会長を退職することとなりました。縁あって明治以来120と余年の長い伝統ある松江商業高校に勤務し、特色のある商業教育に携わることが出来たことを光栄に思っております。コロナ禍という前代未聞の環境の中で、本当に多くの方々のご理解とご協力をいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。これからの益々の発展を祈念して結びとさせていただきます。どうもありがとうございました。
平素より本校の教育振興のため格別のご支援、ご協力を賜っておりますことに厚く御礼を申し上げます。今年度は5月に新型コロナ感染症が5類に移行されることによって、社会経済活動が再開し学校生活もほぼ通常通り動きだしております。
1学期の終業式では、高校総体を始めとして、部活動で全体的に成果が上がってきたこと、課題は抱えながら、個人でも上位大会への進出が増えたこと、ビジネス計算競技大会珠算の部、また簿記競技大会で全国大会出場など成果が上がりつつあることなどを紹介しましたが、終業式後に次のようなイベントがありました。
TVでも報道されましたが、「商業研究部」は、今年度白潟エリアの活性化について調査研究をしています。この活動の一環で、7月22日(土)に白潟本町商店街・北天神商店街にて開催された「まつえ土曜夜市」に出店しました。これまで、商業研究部が開発した商品を販売したほか、ステージでは吹奏楽部の松商メドレー、茶華部は老舗中村茶舗とのコラボで、抹茶レモンサイダーを提供。販売ブースでは松江工業高校の生徒さんと一緒に松江農林高校のジャムも販売しました。地域の方とのたくさんの交流もでき、松江市の抱える商店街の活性化について考察を深める良い機会となりました。そして生徒商業研究発表会で堂々とその実践を発表しました。地域の活性化にチームで寄り添った面白い企画になったと思います。ここからは私見ですが、これ一つ取り上げても、考え方によって生まれてくるものは大きくちがってくると思います。「人口減少に悩む商店街にかつての盛り上がりを取り戻す伝統復活なのか」それとも「商店街そのものを知らない世代の人たちも集まってくる令和の新しい商店街を創造するのか」両者それぞれに分析の方向性や度合いが変わってくると思います。今後が楽しみです。
さて、2学期の出来事では、吹奏楽部がマーチングで2年連続して全国大会に出場することになり、大阪城ホールで演奏し銅賞に輝きました。また、9月末から松江城周辺で行われた「松江水燈路」では美術部の生徒の作品がグランプリになりました。さらに、島根県高校美術展において、美術部の共同制作で彫刻「blow out」が来夏に岐阜県で行われる全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門に島根県代表として推薦されるなど、文化部も力を発揮しています。また、課題研究班はサンラポーむらくもとコラボし「秋に食べたい弁当」の開発を行い実際に販売しました。こうして今年は地域とのつながりや地域産業とのつながりもメディアなどに取り上げてもらっております。
学校行事に目を向けると、先ずは夏休み明けの瑞木祭です。文化祭会場を学校・県民会館、体育祭会場を総合体育館と変えながらの3日間開催、そこには新しいことへのチャレンジとプログラムにも数々の工夫が見られました。PTAの方々と一緒に活動することもできました。もう一つは、商業高校ならではの学びの集大成として、12月2日(土)・3日(日)には「松商だんだんフェスタ」を、今年は入場制限なしで実施することができ、7129名のお客様に来ていただきました。ステージイベントやフードコートの復活、電子マネー決済という挑戦もありました。
以上、良いことばかり列挙しましたが、動き出せば動き出した分だけ課題は課題として見えてきました。しかし同時に、そこには試行錯誤した者のみがわかる経験知が生まれています。私たち生徒・教職員は、諸先輩方が連綿と築いてこられた輝かしい歴史とよき伝統・校風を受け継いでいくとともに、地域の期待と時代の要請に応えるべく、新たな歴史を刻み、夢と活力あふれる学校づくりに邁進していく所存です。今後ともよろしくお願い申しあげます。
皆さまにおかれましては平素より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚く感謝申し上げます。振り返りますと、昨年度までは新型コロナウィルスの影響で学校生活にも様々な影響があり、生徒達は臨時休校や部活動制限などでなかなか思うように学校生活が送ることが出来ませんでした。それまで当たり前にできていたことが実は当たり前ではなかったのだということに空しさも覚えました。さらに3年という歳月は中学や高校生活が3年間であるということを考えると、学校行事などで先輩から後輩へ引き継ぐ事が出来ない、つまり伝統が途絶える危機にあるということになります。コロナ以前の高校生活を知らない世代が在学しています。この状況を踏まえて、今年度に強く意識するのは「伝統をいかに継承するか」「未来をいかに創造するか」ということです。
開校記念日にあたる5月30日には、明治33年開校以来の写真や文書などを展示している「松商Hitory室」と、本校に在籍した版画家の作品を展示している「平塚運一版画館」が開放されました。生徒による課題研究班の一つの班が案内のチラシを作ってPRをしてくれました。先達の偉業を在学生たちが知る良いきっかけになりました。今後、瑞木祭やだんだんフェスタなどの折にも皆様に見ていただけるよう考えています。
また、7月8日にはコロナ禍で延期を余儀なくされていた「一般財団法人振商会創立60周年記念式典」が盛大に開催されました。一般財団法人振商会の皆様方には、特に奨学金制度、部活動表彰、振商会館の利用等々、学校生活全般にわたって多大なるご支援とご協力をいただいております。そして、同じく3年前には出来なかった「島根県立松江商業高等学校創立120周年記念祝賀会」「振商会創立120周年記念祝賀会」「一般財団法人振商会創立60周年記念祝賀会」を併せて開催することが出来ました。お集まりの方々は待ちに待った祝賀会ということで旧交を温め、しばし時を忘れて歓談にふけっておられました。また、DVD上映を通して、本校開校以来の数々の変遷と、脈々と受け継がれている先達の偉業に触れ、ただただ頭が下がる思いでした。
さて、一学期の状況を一言述べますと。今年度は学校生活もほぼ通常通り動きだし、勉強や部活動に打ち込む元気な姿が見られるようになりました。高校総体では、女子バドミントンが団体優勝、さらにダブルス1ペアとシングルス1名が全国大会インターハイの出場権を獲得しました。総合成績も順位を上げ、女子総合は昨年の4位から今年は3位、男子総合は昨年の20位から今年は16位、男女総合は昨年の8位から今年は4位に向上しました。あと2点で3位というところでした。輝かしい過去の記録を見ると、近いところで2018年に女子の総合優勝があるので、そろそろ、令和の時代に総合優勝の名を記しても良いのではないかと期待しています。そして、水泳部がバタフライ200㍍で大会新記録を出して中国大会へ(その後、全国大会へ出場)、陸上競技部、女子バスケットボール部、女子サッカー部、男子ソフトテニス部、弓道部、剣道部、卓球部、男女バドミントン部が中国大会に出場しました。これだけたくさんの上位大会出場は近年にはなかったのではないかと思います。その他の部活動も、ベスト4やベスト8等、自分たちの掲げた目標に向かって向上し、全体的なレベルアップや個人の活躍も目立ってきたように感じています。また、ビジネス計算競技大会珠算の部で個人1名が、また簿記競技大会では団体1位で全国大会出場権を獲得し、成果が上がりつつあります。これを弾みにいい意味で連鎖が広がって行くと良いと思います。
120周年記念式典の折には、「不易と流行」と言う言葉が紹介されました。江戸時代の俳人、松尾芭蕉にまつわる「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず」と言う言葉は、即ち、「不易」という変わらないもの、いつの時代にも軸となるものの上に、「流行」という進取の気風を積極的に取り込むことが大切だということです。私はさらに、「温故知新」という言葉で生徒たちに語りかけています。漢文で読み下すと「故きを温ねて、新しきを知る」となります。元は論語という書物にある言葉ですが、「故きを温ねて、新しきを知れば、以て師たるべし」と続きます。「師」というのは「先生」のことで、「人の師(先生)になる資格がある」という文脈です。この際、少し拡大解釈して「新しい時代の先達・リーダー、開拓者・パイオニア」になると言いたいところです。
私たち生徒・教職員は、諸先輩方が連綿と築いてこられた輝かしい歴史とよき伝統・校風を受け継いでいくとともに、地域の期待と時代の要請に応えるべく、新たな歴史を刻み、夢と活力あふれる学校づくりに邁進していく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

令和5年度の新学期が始まりました。昨年はリモートによる始業式でしたが、今年は体育館で一堂に会することができました。入学式も無事に終わり学校も賑やかになってきました。今年の新入生は、新型コロナウィルスが猛威を振るう真っ只中で中学校生活を送ってきました。数々の制約の中で、勉強への不安や学校行事の楽しみも半減していたのではないかと思います。私たち高校でも昨年は臨時休業や行事の縮小や延期などで我慢して耐える日々が何度もありました。当たり前にできていたことが実は当たり前ではなかったのだということを何度も思いました。しかし逆に、むしろ新入生の皆さんはマスク生活や黙食が日常生活だったのかと思うと三年間という月日の大きさを感じます。しかし、もう、今年はコロナに向き合って4年目になります。感染症対策は油断なくしっかりとやらなければなりませんが、世の中も次第に動き出してきました。やがてコロナが5類になり落ち着くにつれて、部活動も授業や検定・資格取得にも時間を確保して打ち込むことが出来るようになるでしょう。また、課題研究や学校行事などもこれまで以上に地域社会の人たちと触れ合うことが多くなってくるでしょう。それだけ新しい発見や出会いもあり、チャンスも広がってくると思います。ぜひ高校生活で努力が報われる充実感や達成感を味わってほしいと思います。
おそらく世の中も変わっていきます。私たちはコロナ禍の影響下で、ICT機器の普及やリモート会議、テレワーク等々の工夫で生活を維持してきました。しかし今や便利さの反面、やはり対面の方が良く伝わるという反省も出てきています。さらに現代の社会は、ここ十数年間、AI(人工知能)、SDGs(持続可能な開発目標)、カーボン・ニュートラル(脱炭素)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、Society5.0等々の新語が示すように、大きな変革期にあり予測不可能な社会です。しかし、今やそれさえ本当にこれでいいのか検証すべき時に来ているのではないかとまで思います。
先日、ふと次のような言葉を思い出しました。とても有名な四字熟語で中学校の教科書にも載っている言葉です。それは「温故知新」と言う言葉です。漢文で読み下すと「故きを温ねて、新しきを知る」となります。意味は「昔から伝わっているものをよく学んで理解し、新しい知識や知恵を得ること」です。元は論語という書物にある言葉ですが、この後にはさらに続く言葉があります。「故きを温ねて、新しきを知れば、以て師たるべし」「師」というのは「先生」のことで、「人の師(先生)になる資格がある」という文脈です。少し拡大して解釈すると「新しい時代の先達・リーダー、開拓者・パイオニアになることが出来る」と読み替えてもいいでしょう。つまり、こういう時代の変わり目に生きるためには、昔のことをよく知っているだけでは足りないのです。新しいものばかり追い求めても足りないのです。「伝統をいかに継承するか」ということと、「未来をいかに創造するか」ということの二つの視点を持って考える必要があると思います。少し大きなことを言いましたが、大きな志を持つと周りの広い世界が見えてきます。そして、小さな努力を積み重ねていくことの大切さにも気づきます。大きな志をもって小さな努力を着実に積み重ねると良いと思います。今年度は以上のことを意識して進んでいきたいと思っていますのでよろしくお願い致します。

4月に着任して以来、すべての始業式・終業式について、感染症対策のために、別室から配信する動画を各クラスで視聴する形で行ってきましたが、3学期の終業式は体育館で全校生徒が集合して行うことが出来ました。マスク越しとはいえ、実際に顔の動きを見ながら話すことができて、話しやすく感じました。以下はその時の要旨です。
【 令和4年度 3学期 終業式(体育館にて) 】3月24日
おはようございます。令和5年3月24日(金)、ついに体育館で終業式を行うことが出来ましたね。長いコロナ禍の影響で、この一年間、リモートによる始業式や終業式が続いていましたが、この日が来ました。まだまだ感染症対策はしっかりと行うことは重要ですが、世の中も次第に動き出してきましたね。
2学期の終業式でも言いましたが、ここ数年間はあらゆる学校の教育活動が新型コロナウィルスの影響を受けてきました。四月に新学期が始まったときから、ずっと私の念頭にあったことは「いかにして勉強や部活動や学校行事を復活させるか」という課題でした。そして、3学期は短いけれどすべてにおいて一年間の成果が問われるまとめの学期ですとも言いました。一人一人が授業や部活動はもちろん、資格取得や進路選択において満足のいく結果を得られるか、等々。それぞれに自分の目標を定めて、報われる努力をしましょうと言いました。
期待通り、皆さんは1,2学期の部活動や学校行事を数々の制限は付きながらも成功させました。それに続いて、3学期は学習面でも、ちょうど学校入り口の看板にもあるとおり、検定試験の合格率や上位資格の取得、さらに進路実績も上々でした。国ビの修学旅行も復活しましたね。勉強や部活動に打ち込む元気な姿、そして成果が上がってきたことが何よりです。確かに動き出せば動き出した分だけ課題は課題としていろいろと見えてきますが、いい意味でこれからも良い連鎖を続けていきましょう。
さて、少し前にこんなことがありました。松江商業高校にある企業の方が3人で来られました。年配のベテランの方1人と若い方2人でした。掃除時間中だったので玄関のところで掃除をしている生徒を見て年配の方が若手の2人に向かってこう言いました。「今はここに掃除監督の先生がいないけれども、この生徒たちはしっかりと掃除をしているよね。これが本当だよ。この生徒たちは監督が見ていなくても何をすべきかわかっていて、それが実際に実践出来るんだ。」と。企業の方ですから、見るところは見ていますよ。人を見る目は厳しいです。
また、記憶に新しい先日、1・2年生を対象にした企業説明会が本校で行われましたよね。後で、ある大手企業の担当の方がおっしゃっていました。「私は2月から昨日までに、各地の企業説明会に出かけているが、松江商業の生徒が一番良かった。しっかり挨拶してくれるし、聞く態度も良く、意欲的だった。」ということでした。たいへん嬉しい言葉をいただいたと思うと同時に、「信用を得るということ」「相手を本気にさせるということ」とはこういうことの積み重ねではないかと思いました。
3年生が卒業して、これからは1、2年生の皆さんが学校生活を支えていきます。もうすぐ新入生が入学してきます。しっかりと引っ張ってあげてください。勉強の仕方を教えてあげてください。検定の対策を教えてあげてください。部活動の面白さを教えてあげてください。それと部室はきれいですか。見学に来た新入生に対して恥ずかしくない先輩としてどうあれば良いですか。
世の中は、やがてコロナが5類になり落ち着くにつれて、確実に動き出すでしょう。これからは今までよりも地域や学校外の人との関係も多くなってくるでしょう。それだけ見られることも増えてくるでしょうが、それだけ新しい出会いもあり、チャンスも広がってくるでしょう。あなたはどんな未来を想像しますか。
以上を春休みの宿題として自ら考え、決意も新たに新学期がスタートできることを願っています。
本日こうして2学期の終業式を迎えることが出来ました。大雪への心配から一日繰り上げての終業式となりました。11月頃には、全校生徒が体育館に集まって終業式が出来るかなと思っていましたが、やはり世間のコロナ禍の勢いが止まらない状況もあって、オンラインによる終業式となりました。
年末ですので、ざっと今年を振り返ってみましょう。ここ数年間はあらゆる学校の教育活動が新型コロナウィルスの影響を受けて、自粛・延期・中止などという判断をせざるを得ない環境にあり、先の見えない不安の中にありました。四月に新学期が始まったときから、ずっと私の念頭にあったことは「いかにして勉強や部活動や学校行事を復活させるか」という課題でした。今なお収束する様子の見えないコロナ禍ですが、高校生活が3年間である事を考えると、経験者がいなくなって受け継いできた伝統が途絶えてしまします。それでもコロナに向き合って3年目、相応の知恵を絞って行事を精選し「何をどこまで行うことが出来るのか」を心配する毎日でした。
そんな矢先のこと、4月22日から臨時休校に入ることになりましたね。そして、保健所とのやりとり、健康観察、PCR検査等を行いながら学校再開の日を探る日々でした。その後、一度は臨時休校を延長しましたが、幸い28日に休校を終え、ゴールデンウィーク開けの5月6日から全校で授業再開をすることが出来ました。その後は、1学期の終業式でも話しましたが、勉強や部活動に打ち込む元気な姿が見られるようになったこと。そして、高校総体を始めとして、部活動で成果が上がってきたこと、夏に向かって、それぞれの部活動で、掲げた目標に向かって勢いが出てきたと話しました。また、ワープロや簿記等の各種競技大会でも全国大会出場権を獲得したことなど、いい意味で連鎖が広がっていったと話しました。
その流れは2学期に入っても続き、11月には吹奏楽部がマーチングコンテストで全国大会に出場しました。本校初の快挙です。さらにちょうど今週から女子バスケットボール部がウインターカップ2022全国大会に出場し、良い意味で勢いが止まりません。また、地道な活動も注目されています。今週初めのことです。日本政策金融公庫「高校生ビジネスプラン・グランプリ」に10年継続して応募したことが表彰されました。全国で9校しかない、中国地区では初めての栄誉です。まだまだ言い足りませんが、我田引水のごとく手前味噌のごとく引用しましたが、それほど文武両道を掲げる本校としては嬉しい出来事でした。
さて、2学期は学校行事が多いのも特徴です。学園祭が、ここ2年間はコロナ禍で2日開催だったものが、3日間開催をすることが出来、生徒会もおもしろい企画を考えてくれました。ロードレースや球技大会なども実施できています。そして、商業高校ならではの魅力的な学びの一つとして、「松商だんだんフェスタ」を入場者数に制限はありながらも、12月に開催できたこと。そこには普段はおとなしい生徒達のビジネスマナーに則った元気の良い声と活動がありました。また、復活を願う外部の人々の声も多く聞きました。確かに、動き出せば動き出した分だけ課題は課題としていろいろと見えてきますが、生徒が生き生きと生活してこその学校だと思います。また、先生方も忙しい中、9月には生徒商業研究発表大会の中国大会を運営し、11月にはその全国大会を運営しています。何かと行事の多い2学期でしたが、入場者制限はありながらも、ほぼすべての予定をこなすことが出来ました。
さて、そうなると3学期は何が課題でしょうか。3学期は短いけれどすべてにおいて一年間の成果が問われる学期です。一人一人が授業はもちろん、きちんと単位を修得し、どれだけ資格取得が出来るか、進路選択や進路決定において満足のいく結果を得られるか、等々。たしかにコロナ禍で出来にくい状況はありましたが、そのせいにしてばかりはいられません。どんな環境の中でも自分の目標を定めて、いま出来る努力を始め、自らの道を開拓していかなければなりません。冬休みには今年やり残したことがあればそれをやり、3学期に自分自身納得のいく成果につながるように、しっかりと計画を立てて実行をしてください。
最後に、クリスマスも近いことですのでプレゼントを贈ります。プレゼントとは言っても、私が編集した言葉のプレゼントです。世界にはこういう言葉を贈る風習のある国もあるようです。「昨日よりも今日よりも、明日は何かを変えてみよう。」新しい年が充実し、さらに、これまでとはひと味違う年になる事を期待しています。
【 次なるステージへ 】
本日、1学期の終業式を迎えることが出来ました。始業式は放送で行い、入学式は1年生のみ体育館で短縮・簡素化して行いました。1学期が始まっても、臨時休校や部活動の制限、中間試験の中止等、学校生活にも様々な影響がありました。そして、やはり今も新型コロナウィルスの第7波とやらに脅かされて終わる1学期になってしまいました。
しかし、振り返ってみると、コロナと向き合って3年目、何かが変わってきたと私は思います。4月こそコロナ禍の影響がありましたが、5月にはほぼ落ち着き、勉強や部活動に打ち込む元気な姿が見られるようになりました。そして、5月末から行われた高校総体では、振商会からも激励をしていただきましたが、3つの団体競技(女子バドミントン部・女子バスケットボール部・女子ソフトボール部)と個人競技(バドミントン部のダブルス1ペアとシングルス1名、弓道部の個人1名、)等で、近年にない数の全国大会インターハイの出場権を獲得しました。加えて、サッカー部・卓球部・水泳部は中国大会に出場し、その他の部活動も自分たちの掲げた目標に向かって勢いが出てきたように感じます。直近では野球部も快進撃を続けています。
さらに、各種商業系の競技大会(ワープロや簿記、英語弁論等)でも全国大会出場権を獲得して好成績を収め成果が上がりつつあります。総体壮行式や報告会でも話しましたが、身近にいる先輩やクラスメイトの活躍に刺激されて、これを弾みに「私も。私も。」と良い意味で連鎖が広がって行くと良いと思います。
そして学習面ですが、郵送される通知票や担任との個人面談等を通して1学期の自分の取り組みを振り返る事が必要です。何が出来て何が出来なかったのか、その原因は何なのか。目標を掲げて地道な努力をするという点で、その姿勢は部活動と何ら変わるところではありません。ぜひ、2学期はさらに成績も向上させ文武両道を成し遂げてほしいと思います。
コロナと向き合って3年目、もう一律に何でも中止というわけにはいきません。厳しい状況は続きますが感染症対策には十分注意しつつも、充実感や達成感のある本来の学校生活を取り戻せるように、そして学校行事の再検討など工夫・努力していきますので、今後ともよろしくお願いします。
【 夏休みを迎えるにあたって 】
これから約一ヶ月夏休みに入りますが、私が高校生の時に担任の先生が話された言葉を紹介します。 「君子、三日会わざれば、刮目して見るべし。」
元の話は中国の古典『三国志演義』にあるのですが、呉の国の武将で呂蒙という人の話です。呂蒙は学問が嫌いで勉強しなかったため、世間から笑われていました。それを残念に思った呉王の孫権は彼が変わることが出来るようにいろいろな書物を読むように勧めました。すると呂蒙は、自分のためを思って言ってくれる孫権の言葉を受け止めて、その後たいへんな努力をするようになりました。ある日、日頃から彼を軽蔑していた呉の国の魯粛という人が会って話をしてみると、呂蒙が以前とは比べものにならないほど豊かな学問と知識を備えた人物になっていて、魯粛はたいへん驚いた、ということです。この話を踏まえた言葉が「君子、三日会わざれば、刮目して見るべし。」という言葉で、(解説)「立派な人というものは、別れて三日もあると大いに成長しているものだ。だから、次に会ったときは目を見開いてしっかりと見なければならない。」という意味です。自覚と努力によって人は大きく成長するものです。
この話のように、生徒の皆さんにも自分の成長が実感できる、そしてそれが周囲の人にも伝わるような夏休みを過ごしてほしいと願っています。
いよいよ高校総体が間近に迫ってきました。そして、総体パワーアップ期間が始まりました。放課後の校舎内外で一生懸命練習している元気な姿をたくさん見かけます。
今年も新型コロナウィルスの影響で、練習試合ができなかったり、日々の練習などにも数々の制約があったり、満足な部活動はできなかったかもしれませんが、それでもオミクロン株に負けない強い思いに支えられて今日まで来ています。今後も決して安心はできませんが、これまでの不安や悔しさをバネにし、すべてをプラスのエネルギーに変えて、挑戦してほしいと思っています。
壮行式ではこんな話をしました。古来、戦いに勝つ3つの条件として、「天の時・地の利・人の和」という言葉があります。「天の時」これは「自然の条件や運勢が良いこと、チャンスが訪れること」等を表します。「地の利」これは「地理的な条件が良いこと、相手より有利な立ち位置にいること」です。「人の和」これは「人々の気持ちが一つになっていること」です。漢文でおなじみの「孟子」に出てくる言葉ですが、その中でも「最も大切なものは人の和である」と言っています。なぜだかわかりますか?(尤も、天の時や地の利は私たち個人の力ではどうしようもないですけどね)
各部活動ともお互い励まし合い一致団結して、これまで蓄積してきた力を存分に発揮してくれることを期待しています。そして、今回は出場しないけれども、それぞれ自分の目指す次の大会に向かっている人もいるはずです。また、文化部の多くは秋に向かって今からスタートしましょう。全力をぶつける時期や状況は様々でしょうが、このパワーアップ期間を皮切りに、一層の磨きをかけてください。松江商業高校の全体が、お互いの活躍の場を、応援し励まし合い、充実感を味わえるように願っています。

別天地 やがて明けゆく 春の海
かつて西へ向かった道を、時を経て今、東へ向かう。
若き日に思い出を残して旅立った地は、
時代の流れに様変わりをして、
新たな勢いのもとに進もうとしている。
期待と不安とが入り交じる不透明な未来。
しかし、水平線は明るさを増し、
生まれ変わった陽が昇ることを教えてくれる。

このたびの異動で赴任した校長の木村文明です。前任校が浜田商業高校でしたので、同じ「商業」つながりということで、ビジネスマナーを徹底し、多くの資格を取得し、勉強と部活動の両立に打ち込んで、実績をあげている松江商業高校のことは、あるときは一つの目標として、またあるときはよき仲間として外から見ていました。
実際に来てみると、さすがは創立120周年を誇る伝統の数々、様々な設備を備えた校舎の広さ、さらには自然環境の美しさまで加わって、連日のコロナ報道で悶々としていた気持ちも吹き飛ぶ思いに変わりました。
コロナの影響で、春休み中の部活動がない静かな校舎でしたが、いよいよ新学期ということで、生徒の皆さんが登校して学校らしくなりました。どんな年になるのでしょうか。今から期待しています。どうかよろしくお願いします。